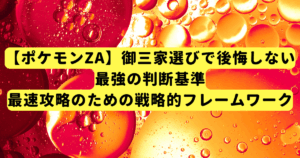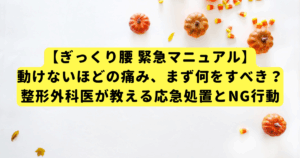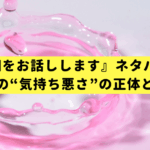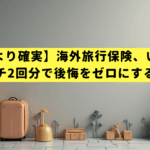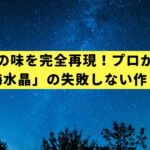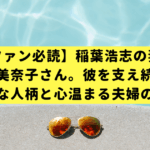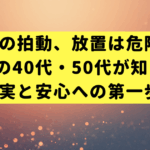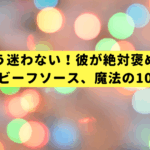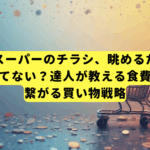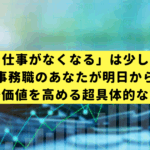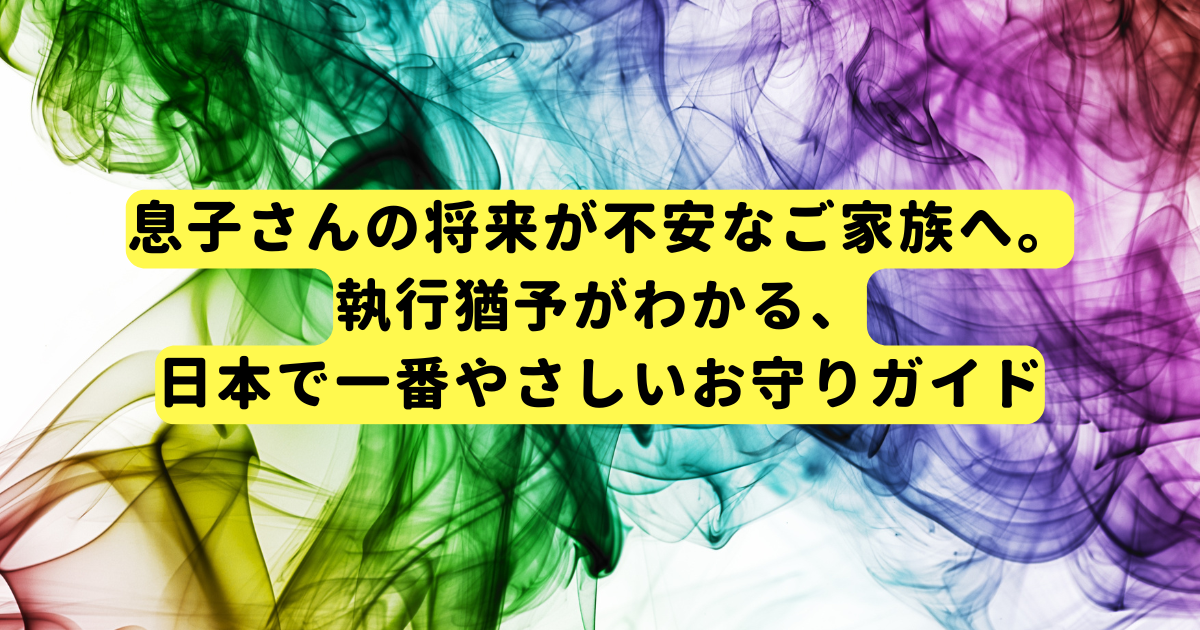
息子さんが逮捕され、聞き慣れない「執行猶予」という言葉を前に、どうしていいか分からず、ただ不安な日々をお過ごしのこととお察しいたします。今、息子さんのことで、ご飯も喉を通らないほどご不安な毎日をお過ごしのことでしょう。
まず、ご安心ください。執行猶予は、社会の中でやり直すためのチャンスであり、そのために今、ご家族ができることは、たくさんあります。
この記事は、難しい法律用語を解説するものではありません。これまで300以上の家族に寄り添ってきた専門家があなたの隣で、心の不安に寄り添いながら、今日からできることを具体的にお伝えする「お守り」のようなガイドです。法律のことは、今は分からなくても大丈夫です。
この記事を読み終える頃には、きっとこうなっているはずです。
- 「執行猶予」が、希望の制度であることが分かります。
- 息子さんのために、ご家族が「今すぐやるべきこと」が分かります。
- 先の見えない不安が和らぎ、少しだけ前向きな気持ちになれます。
まだ、希望はあります。そして、あなたにできることは、たくさんあります。一緒に、一つずつ、進んでいきましょう。
まず、ご家族の不安を少しだけ軽くさせてください
「執行猶予」と聞いて、「刑務所」「前科」「息子の人生はもう終わりだ」といった言葉が頭をよぎるのは、当然のことです。大切なご家族のことですから、誰でもそうなります。そのお気持ちは、決して間違っていません。
しかし、その不安のあまり、希望まで手放してしまう必要は全くありません。
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: まず、「前科がついたら、人生は終わり」という考えから、少しだけ距離を置いてみてください。
なぜなら、「息子の人生はもう終わりですか?」というご質問は、私たちがこれまで300以上の家族から受けてきた、最も切実なご質問だからです。その言葉の裏には、世間からの偏見や就職への絶望といった、深い愛情ゆえの底知れぬ不安があります。しかし、私は断言できます。決して、終わりではありません。
専門用語は使いません。「執行猶予」は、社会でやり直すための「チャンス」です
テレビのニュースなどで聞く「執行猶予」という言葉には、どこか冷たく、怖い響きがあるかもしれません。
ですが、この制度の本当の目的は、罰を与えることではありません。
裁判官が最も重視しているのは、「罪を犯した人が、本当に反省し、社会の中で家族や周りの人々のサポートを受けながら、もう一度やり直せるか」という点です。
つまり、裁判官が「刑務所に入れるよりも、社会の中でご家族のサポートを受けながら生活する方が、本人の立ち直りにつながる」と判断した場合に、執行猶予の判決を出します。
ですから、ご家族の支えこそが、執行猶予を得るための最大の鍵になると言っても過言ではないのです。
**
🎨 デザイナー向け指示書:インフォグラフィック
件名: 「人生の分かれ道」執行猶予の概念図
目的: 執行猶予が「社会の中で更生するチャンス」であり、そこに「家族の支え」が不可欠であることを、視覚的に瞬時に理解させる。
構成要素:
1. タイトル: 人生の分かれ道
2. ステップ1: 上部に「判決」というボックスを配置。
3. ステップ2: 「判決」から左右に矢印を分岐。左の矢印の下に「実刑判決」と記載し、その先に「刑務所」のシンプルなイラストを配置。
4. ステップ3: 右の矢印の下に「執行猶予判決」と記載し、その先に「自宅で家族と生活する」様子の温かいイラストを配置。
5. 補足: 右側の「自宅で家族と生活する」イラストの横に、「ここでの家族の支えが、未来を創る!」という応援メッセージを吹き出しで追加する。
デザインの方向性: 全体的に柔らかく、希望を感じさせる暖色系のカラーを使用。イラストはシンプルで親しみやすいタッチでお願いします。
参考altテキスト: 執行猶予と実刑判決の違いを示す図解。実刑は刑務所へ、執行猶予は家族のサポートのもと社会生活を継続する道へ続くことを表している。
そして、希望を持てるデータもあります。
全ての刑事裁判で起訴された人のうち、約65.3%に執行猶予がついています。(令和4年度)
出典: [令和6年版 犯罪白書](https://www.daylight-law.jp/criminal/ryokei/shikkouyuuyo/3020/) - 法務省, 2024年
もちろん、事件の内容によって大きく異なりますが、決して低い数字ではないことがお分かりいただけると思います。希望は十分にあります。
息子さんの未来のために。ご家族が「今日から」できる3つのこと
「希望があることは分かったけれど、具体的に何をすれば…?」
そのお気持ち、よく分かります。
ここからは、息子さんの未来のために、ご家族が「今日から」できる、最も大切な3つの行動をお伝えします。
1. 被害者の方へのお詫びと「示談」を全力で進める
何よりもまず、息子さんが起こしてしまった事件の被害者の方へ、誠心誠意の謝罪と被害の弁償をすること、つまり「示談」が不可欠です。裁判官は「当事者同士で解決が進んでいるか」を非常に重く見ています。これは通常、弁護士を通じて行いますので、すぐに弁護士に相談し、示談交渉を始めてもらうことが最初のステップです。
2. 「これからは家族が監督します」という計画を準備する
次に、「これからは家族が責任をもって本人を監督し、二度と罪を犯させません」という具体的な計画を立て、それを書面にして裁判官に伝えることが極めて有効です。
例えば、以下のような内容です。
- 判決後は実家で同居し、生活を監督する。
- 定職に就くまで、家族が経済的・精神的にサポートする。
- 定期的に通院が必要な場合は、必ず付き添う。
3. 本人に反省を促し、その気持ちを書面にしてもらう
そして、息子さん自身が自分のしたことを心から反省している態度を示すことも重要です。ご家族として、その反省を促し、見守ることが大切になります。そして、その反省の気持ちを手紙などの書面にしてもらい、裁判所に提出することも有効です。
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: 最も避けたいのは、ショックと混乱のあまり「弁護士に任せておけば大丈夫」と受け身になってしまうことです。
なぜなら、判決前の「今」こそ、ご家族が動ける最も重要な時期だからです。被害者への謝罪の気持ちや、本人を監督する覚悟といった「ご家族の姿勢」は、弁護士だけでは示すことができません。裁判官も、同じ人間です。家族が一丸となって更生を支えようとしている姿は、必ず良い心証を与えます。
✅ 弁護士への相談時に確認したいことリスト
- 示談交渉は、いつから始めてもらえますか?
- 家族として、示談のために協力できることはありますか?
- 家族の監督計画書は、いつまでに、どのように作成すればよいですか?
- 本人の反省文は、どのような内容を書くべきですか?
よくあるご質問:「前科」がつくと、生活はどう変わりますか?
執行猶予判決が出た場合でも、「前科」はつきます。
この「前科」という言葉に、大きな不安を感じる方も多いでしょう。
ここでは、よくいただくご質問にお答えする形で、生活への影響を具体的にお伝えします。
Q1. 今の仕事は続けられますか?
はい、基本的には続けられます。前科がついたことを、自分から会社に報告する義務はありません。ただし、医師や弁護士、公務員、警備員など、特定の資格や職業では法律で制限(欠格事由)が定められており、その職を失う可能性があります。
Q2. 再就職や結婚に影響はありますか?
履歴書の賞罰欄に記載する必要はありますが、正直に話すかどうかは最終的に本人の判断となります。結婚についても同様で、相手に伝える法的な義務はありません。大切なのは、本人が過去と向き合い、誠実に人生を歩んでいく姿勢です。ご家族のサポートが、その支えになります。
Q3. 海外旅行には行けますか?
パスポートの取得は可能ですが、渡航先の国によってはビザの申請時に前科の申告が求められ、入国が許可されない場合があります。特にアメリカなどは審査が厳しいと言われています。
あなたの勇気と愛情が、未来を創ります
この記事でお伝えしたかった、最も重要なメッセージを繰り返します。
- 執行猶予は、終わりではなく**「社会でやり直すためのスタートライン」**です。
- 今、ご家族が動くことが、息子さんの未来を大きく左右します。
- 一人で抱え込まず、私たちのような専門家を頼ってください。
恵子さん、この記事をここまで熱心に読まれたあなたは、すでに息子さんを支えるための、力強い大きな一歩を踏み出しています。その勇気と深い愛情が、必ずや息子さんの未来を良い方向へと導いてくれます。
先の見えない不安で、押しつぶされそうになることもあるでしょう。
そんな時は、どうか一人で抱え込まないでください。
不安な気持ちを、少しでも私たち専門家にお話ししてみませんか。