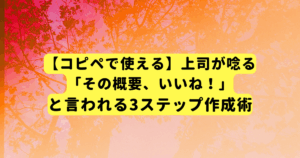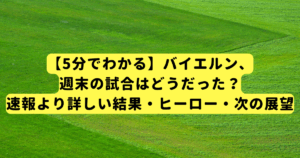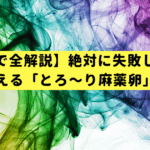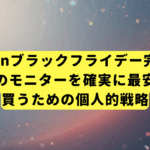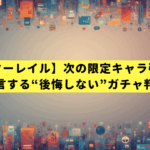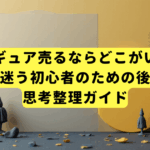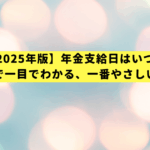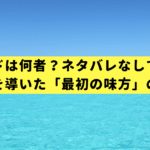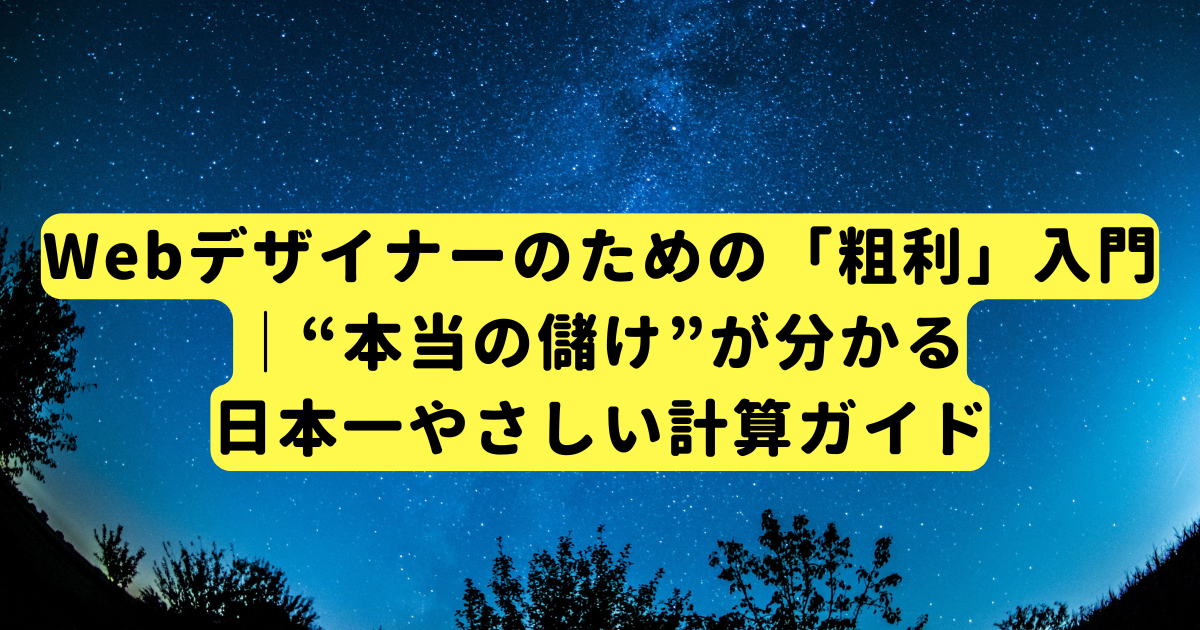
「売上はあるはずなのに、なぜか手元にお金が残らない…」フリーランスのデザイナーとして、そんな不安を感じていませんか?
こんにちは、税理士の坂本です。僕も昔は皆さんと同じデザイナーでした。だからそのモヤモヤした気持ち、本当によく分かります。その原因は、もしかしたら**「粗利(あらり)」を把握できていないからかもしれません。粗利とは、一言でいえば、あなたの仕事の「本当の儲け」**のことです。
この記事は、会計用語が苦手なWebデザイナーのあなたのためだけに書きました。専門用語を極力使わず、「あなたのビジネス」に当てはめて粗利を理解し、計算できるようになることをお約束します。
この記事を読み終える頃には、あなたはこうなっています。
- 「粗利」が何かが、専門用語ゼロで理解できる。
- 自分の仕事の「本当の儲け」を計算できるようになる。
- どんぶり勘定を卒業し、経営者としての第一歩を踏み出せる。
なぜ「売上100万円」でも安心できない?すべてのデザイナーが粗利を知るべき理由
あなたがもし「今月の売上は100万円だ!」と喜んでいるとしたら、少しだけ注意が必要です。なぜなら、その100万円が、まるまるあなたの利益になるわけではないからです。
例えば、100万円のWebサイト制作の案件があったとします。そのために、外部のコーダーさんに50万円、カメラマンさんに20万円を支払ったとしたら、どうでしょう。あなたの手元に残るのは30万円です。この**30万円こそが「粗利」**であり、あなたのビジネスのスタートラインとなる利益です。
もし、この粗利から事務所の家賃や通信費、PCのローンなどを支払っていくと考えると、「売上100万円」という数字だけを見て安心するのは危険だと感じませんか。
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: 私がデザイナーさんから受ける相談で断トツに多いのが、「売上はあるのにお金がないんです」というものです。これは決してあなただけの悩みではありません。
なぜなら、ほとんどのクリエイターは素晴らしい作品を作ることには長けていますが、その価値を「利益」という数字で把握する訓練を受けていないからです。原因はほぼ100%、この「粗利」を計算していないことにあります。この記事が、その最初のステップになれば嬉しいです。
たったこれだけ!デザイナーの「粗利」計算式と“直接かかった費用”の見つけ方
では、どうすれば粗利を計算できるのでしょうか。安心してください。計算式は驚くほどシンプルです。
粗利 = 売上 - 売上原価
「売上」は、クライアントに請求した金額なので、すぐに分かりますね。
問題は**「売上原価(うりあげげんか)」です。この言葉にアレルギー反応を起こす必要はありません。これは、「その仕事のために、直接かかった費用」**と覚えてください。
Webデザイナーであるあなたの「売上原価」になるのは、主に以下のようなものです。
- 外注費: コーディングやイラスト、ライティングなどを外部に依頼した費用
- 素材購入費: その案件のために購入した有料フォントやストックフォトの費用
- サーバー費: クライアントのウェブサイトを管理している場合のサーバーレンタル費用
一方で、事務所の家賃やインターネット代、Adobe CCの月額料金などは、この仕事があってもなくても発生するものですよね。それらは売上原価には含めません。
この区別を視覚的に理解するために、簡単なフロー図を用意しました。
**
🎨 デザイナー向け指示書:インフォグラフィック
件名: Webデザイナーの売上原価 見分け方フロー
目的: 読者が自分の経費を「売上原価」と「それ以外」に正しく仕分けられるようになること
構成要素:
1. タイトル: それって「売上原価」?簡単YES/NOチャート
2. スタート: 「ある費用(出費)を思い浮かべてください」
3. 質問: 「もし、この案件が“なかった”としたら、その費用は発生しましたか?」
4. → NO(発生しなかった)の場合: 「おめでとうございます!それが“売上原価”です!(例:外注費、案件用の有料素材費)」
5. → YES(発生した)の場合: 「それは“売上原価”では“ありません”(例:事務所の家賃、Adobe CCの月額費、通信費)」
デザインの方向性: 親しみやすい手書き風のイラストとシンプルな線で構成。色はグリーンを基調とし、安心感を与えるデザインにしてください。
参考altテキスト: Webデザイナーが売上原価を見分けるためのフローチャート。「この案件がなければ発生しなかった費用か?」という問いにNOなら売上原価、YESならそれ以外の経費と判断できる。
具体例:売上50万円のサイト制作案件で計算してみよう
言葉だけだと分かりにくいので、具体的な案件で一緒に計算してみましょう。
- 売上: 500,000円
- 外注コーディング費: 150,000円
- 有料ストックフォト代: 20,000円
- 事務所の家賃: 100,000円
この場合、売上原価は「外注コーディング費」と「有料ストックフォト代」だけです。
売上原価 = 150,000円 + 20,000円 = 170,000円
したがって、この仕事の粗利は、
粗利 = 500,000円 - 170,000円 = 330,000円
となります。
どうでしょう?意外と簡単だと思いませんか。この33万円が、あなたのクリエイティブが生み出した「本当の儲け」の第一歩です。
【実践】あなたの仕事の粗利を計算してみよう!よくある費用の仕分けドリル
知識を自分のものにする一番の近道は、実際に手を動かしてみることです。あなたの日常的な経費が、「売上原価」になるかならないか、ここで仕分けクイズをやってみましょう!
デザイナー経費 仕分けチャレンジ!
費用の種類 売上原価? 解説 外注ライターへの支払い ⭕️ 売上原価 その案件がなければ発生しない、直接的な費用です。 Adobe Creative Cloud の月額料金 ❌ 売上原価ではない どの案件にも共通で使う費用。後で計算する「販管費」になります。 事務所の家賃 ❌ 売上原価ではない 売上がゼロでも発生する固定費です。「販管費」に分類されます。 クライアントとの打ち合わせのコーヒー代 ❌ 売上原価ではない 営業活動に関わる費用なので「接待交際費」として扱います。 案件で使用した有料フォント代 ⭕️ 売上原価 その案件のためだけに購入したのであれば、直接的な費用です。 新しいMacBook Proの購入費 ❌ 売上原価ではない 長期間使う機材は「減価償却」という別の考え方をします。
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: 独立したてのデザイナーさんが最も陥りやすい間違いが、Adobeの費用やPCの購入費を「売上原価」に入れてしまうことです。
なぜなら、「仕事に必須の道具だから」と考えてしまうからです。その気持ちは痛いほど分かります。しかし会計の世界では、「特定の案件に直接紐づくか?」という視点が重要になります。この区別ができるようになれば、あなたはもう立派な経営者です。
もっと詳しく知りたいあなたへ【Q&A】
ここまで読んで、さらに疑問が湧いてきた方もいるかもしれません。よくある質問にお答えします。
Q1. 粗利と「営業利益」って何が違うの?
A1. とても良い質問です!粗利から、さらに家賃や通信費、広告費といった「販管費(はんかんひ)」を差し引いたものが「営業利益」です。これは、本業で稼いだ最終的な利益に近い数字です。まずは粗利を理解することが第一歩です。
Q2. デザイナーの粗利率の目安ってどれくらい?
A2. 事業の形態によるので一概には言えませんが、もし外注を全く使わないのであれば、粗利率は90%以上になるはずです。外注が多いビジネスモデルなら、50%〜70%程度が一つの目安になるかもしれません。大切なのは、他人と比較するより、自分自身の過去の仕事と比較して、粗利率が改善しているかを見ることです。
Q3. 粗利を増やすにはどうすればいい?
A3. 方法は2つしかありません。一つは「売上を上げること(単価を上げる、受注数を増やす)」。もう一つは「売上原価を下げること(外注費の交渉、効率化)」です。どちらが自分のビジネスにとって現実的か、ぜひ考えてみてください。
まとめ:あなたの価値を、正しく知るために
お疲れ様でした。これで、あなたも「粗利」の基本をマスターしました。最後に、最も重要なポイントを振り返りましょう。
- 粗利とは、売上から「その仕事に直接かかった費用(売上原価)」だけを引いた「本当の儲け」です。
- デザイナーの場合、売上原価は外注費や案件専用の素材費などが当たります。家賃やPC代は含めません。
- まずは、一番最近の仕事の粗利を計算してみることから始めましょう。
「粗利」が分かると、どの仕事が本当に儲かっているのか、どの仕事が実は赤字すれすれなのかが、数字でハッキリと見えてきます。それは、あなたのデザインの価値を正しく知り、自信を持って価格交渉をするための最強の武器になります。
あなたはもう、どんぶり勘定のデザイナーではありません。自分の価値を数字で語れる、経営者としての道を歩み始めたのです。
さあ、今すぐ手元にある一番最近の請求書と、それに関わる経費の領収書を見て、この記事の通りにあなたの仕事の「粗利」を計算してみましょう!
もし、さらに会計の知識を深めてビジネスを加速させたいと思ったら、次は「会計ソフトを使った簡単な利益管理法」についての記事も、きっとあなたの役に立つはずです。