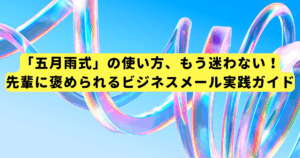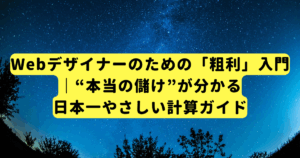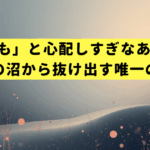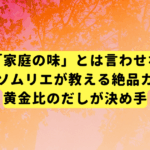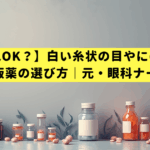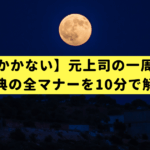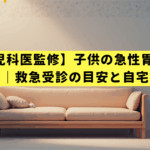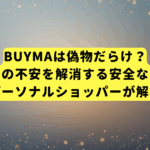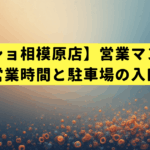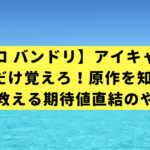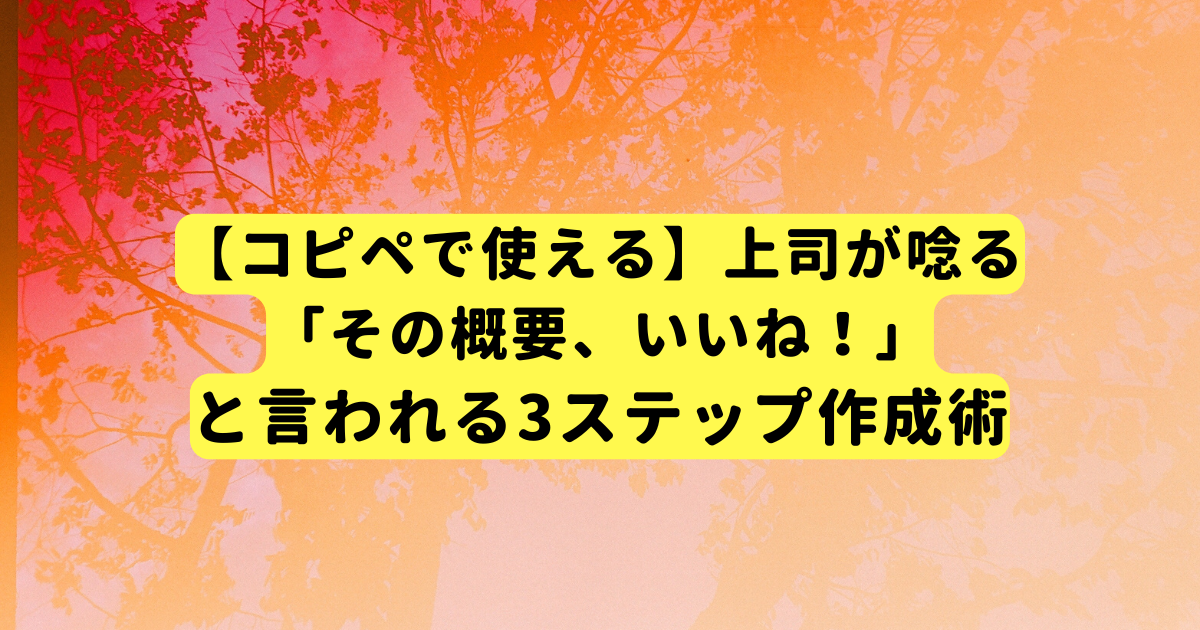
こんにちは。若手ビジネスパーソン向け研修講師の佐藤です。
上司からの「この件、概要まとめといて」という一言で、キーボードを打つ手が止まっていませんか?私も新人の頃、同じ指示に4時間もかけてしまい、結局「要点が分からない」と突き返された苦い経験があります。でも大丈夫、もう迷うことはありませんよ。
ビジネスにおける「概要」とは、単なる要約ではありません。それは**相手の貴重な時間を節約し、次の行動を促すための「戦略的ツール」**なのです。
この記事は、辞書的な意味の解説ではありません。入社2年目の中村さんが明日、上司に「よく分かってるね!」と認められるためだけに書かれた、失敗回避型の実践ガイドです。
この記事を読み終える頃には、あなたはきっと、
- 上司が本当に求めていることを正確に理解できる。
- 明日からすぐに使える、分かりやすい概要の「型」が手に入る。
- 「的外れだったらどうしよう…」という不安が自信に変わる。
はずです。それでは、一緒に見ていきましょう。
なぜ、デキる人ほど「概要」を重視するのか?
まず最初に、なぜ上司は中村さんに「概要」を求めるのでしょうか。答えはシンプルで、上司は常に忙しいからです。
全ての詳細な資料を読み込む時間がない中で、素早く正確な意思決定を下す必要があります。その時、判断の土台となるのが、部下から提出される「概要」なのです。
つまり、「概要」作成は単なる作業ではありません。それは、上司の時間を尊重するという配慮の表れであり、あなたの評価を上げる絶好のチャンスなのです。的確な概要を提出できれば、「彼は要点を掴むのが上手いな」という信頼を勝ち取ることができます。
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: 「頑張ってたくさん書く」ことから、「相手が知りたいことだけを書く」ことへ、意識を切り替えてみましょう。
なぜなら、私の研修で最も多い質問が「どこまで詳しく書けばいいですか?」だからです。その質問の裏には「頑張りが足りないと思われたくない」という気持ちが隠れています。しかし、ビジネスで本当に評価されるのは情報の「量」ではなく、相手の意思決定を助ける「質」なのです。この知見が、あなたの成功の助けになれば幸いです。
評価が上がる「概要」の絶対原則:目的から逆算せよ
では、どうすれば評価される概要が書けるようになるのでしょうか。絶対に外してはいけない、たった一つの原則があります。それは**「目的から逆算する」**ことです。
書き始める前に、まず自分にこう問いかけてみてください。
- 「誰に」(例:直属の上司に?他部署の部長に?)
- 「何をしてもらいたいか」(例:事実を理解してほしい?A案とB案から選んでほしい?予算の承認をしてほしい?)
この「目的」こそが、膨大な情報の中から「何を書くべきで、何を書かなくてよいか」を判断する唯一のコンパスになります。目的が明確になれば、盛り込むべき情報はおのずと決まってくるのです。
**
🎨 デザイナー向け指示書:インフォグラフィック
件名: 評価される「概要」作成の4ステップ・フロー図
目的: 最初に「目的の確認」を行うことが、全体の質を決める土台であることを視覚的に理解させる。
構成要素:
1. タイトル: 評価される「概要」作成の4ステップ
2. ステップ1: 【土台】目的の確認 (誰に? 何をしてほしい?)
3. ステップ2: 情報の収集 (目的に必要な情報だけを集める)
4. ステップ3: 構成の決定 (結論から話す型を選ぶ)
5. ステップ4: 執筆 (簡潔な言葉で書く)
デザインの方向性: シンプルで分かりやすいフラットデザイン。ステップ1が他のステップを支える土台のようなイメージでお願いします。コーポレートカラーの青を基調に、信頼感が伝わる配色を希望します。
参考altテキスト: 概要作成の4ステップを示すフロー図。ステップ1の目的確認が土台となり、情報収集、構成決定、執筆と続くプロセスを表している。
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: 情報の「インプット量」で勝負するのは、今日で終わりにしましょう。
なぜなら、私自身がコンサルタント時代、情報の網羅性こそが価値だと信じて疑わなかったからです。しかし、本当にクライアントから評価されたのは、分厚いレポートではなく、「で、我々は何をすべきか」という問いに最短で答える一枚のサマリーでした。この経験から、ビジネスの価値は「相手を動かすこと」にあると確信しています。
もう迷わない!コピペで使える3つの「伝わる型」と失敗回避チェックリスト
目的が定まったら、次はいよいよ執筆です。しかし、ゼロから文章を組み立てる必要はありません。ビジネスには、情報を分かりやすく整理するための「型(フレームワーク)」が存在します。
今回は、中村さんが明日からすぐに使える、特に強力な3つの型をご紹介します。
- PREP法(結論 → 理由 → 具体例 → 結論)
- 用途: 上司への報告や提案など、相手の承認や判断を仰ぎたい場面で最強の型です。結論から話すことで、相手はストレスなく話の全体像を掴めます。
- SDS法(全体像 → 詳細 → まとめ)
- 用途: プロジェクトの進捗報告や、複雑な事柄の説明など、相手に何かを理解してもらいたい場面で有効です。「まず全体像からお話しします」と始めることで、聞き手は安心して詳細な話に入ることができます。
- 5W1H(Who, When, Where, What, Why, How)
- 用途: 競合サービスの調査報告など、情報を整理して事実を伝えたい場面で役立ちます。この6つの要素を埋めるだけで、報告に必要な情報が漏れなく整理できます。
「評価される概要」と「突き返される概要」の具体例
観点 ❌ 突き返される概要 (新人の頃の私) ✅ 評価される概要 (今の私) 目的の明確さ A社の新サービスについて調査した内容をまとめました。全部で10ページあります。 A社の新サービスについて、我々が対策を検討すべき点に絞って3点で報告します。 一文の長さ 当該サービスは若年層をターゲットとし、サブスクリプションモデルを採用しており、これが収益の柱となっていると考えられますが… A社の新サービスは、若者向けのサブスクリプションモデルです。 事実と意見の区別 A社のサイトはデザインがおしゃれで、若者に人気が出そうです。 A社のサイトには「10代の利用率No.1」との記載がありました(事実)。これは我々の脅威になり得ます(意見)。
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: 完璧な報告書を目指す前に、まずは「30秒で説明できるか?」を自問自答してみてください。
なぜなら、私自身が新人時代、調査した情報を全て詰め込んだ完璧なレポートを提出し、上司に「よくやった。で、君の意見は?30秒で説明して」と返され、頭が真っ白になった経験があるからです。この経験から、要点を簡潔にまとめる訓練の重要性を痛感しました。
最後に、中村さんが今後「概要」を作成する際に、失敗を確実に回避するためのチェックリストを授けます。
【失敗回避チェックリスト】
- 目的(誰に、何をしてほしいか)は明確か?
- 結論から書き始めているか? (PREP法)
- 一文はスマホで読みやすい60文字以内か?
- カタカナの専門用語を「翻訳」しているか?
- 「事実」と「自分の意見」を明確に分けているか?
ここまで分かれば完璧!「概要」に関するQ&A
ここまでお疲れ様でした。最後に、中村さんがまだ疑問に思っているかもしれない点について、Q&A形式でお答えしますね。
Q. 「概要」と「要約」「あらすじ」って、ビジネスではどう使い分けるべき?
A. 良い質問ですね。ビジネスシーンでは以下のように使い分けると明確です。
- 概要: 相手の意思決定を目的とし、情報の背景や要点をまとめたもの。
- 要約: 元の文章の内容理解を目的とし、文章を短くまとめたもの。
- あらすじ: 物語の流れの理解を目的とし、話の筋をまとめたもの。
上司から求められるのは、ほとんどが「概要」だと考えて良いでしょう。
Q. 口頭で「概要説明して」と言われた場合はどうすれば?
A. 基本は文章と同じで、PREP法(結論から話す)を意識してください。「結論から申し上げますと、〇〇です。なぜなら…」と話し始めるだけで、聞き手の理解度は劇的に変わります。時間は1分以内を目安にすると良いでしょう。
Q. 参考にした資料は、どこまで記載すればいいですか?
A. 報告の信頼性を担保するために、出典の明記は非常に重要です。特に、数値データや他社の情報を引用した場合は、末尾に「(出典:〇〇株式会社 Webサイト)」のように、誰が見ても分かる形で情報源を記載する癖をつけましょう。
まとめ:あなたの評価は「概要」で変わる
中村さん、本当にお疲れ様でした。最後に、この記事でお伝えした最も重要なことを振り返りましょう。
- 「概要」は相手の意思決定を助けるための戦略的ツールである。
- 書き始める前に、まず「誰に、何をしてほしいか」という目的を明確にする。
- PREP法などの「型」を使いこなせば、誰でも分かりやすく書ける。
もう大丈夫です。「概要」の作成は、面倒な作業ではありません。それは、あなたの評価を上げ、信頼を勝ち取るための絶好のチャンスなのです。
今日学んだことを武器に、自信を持って明日の業務に臨んでください。応援しています!