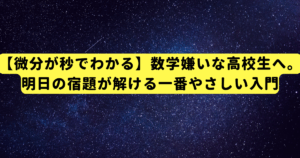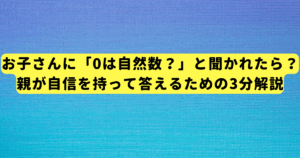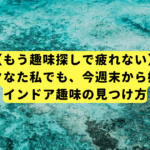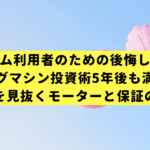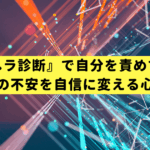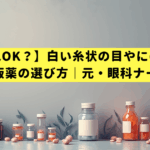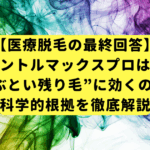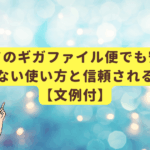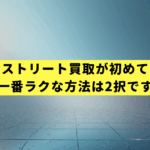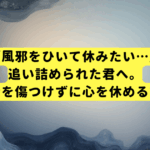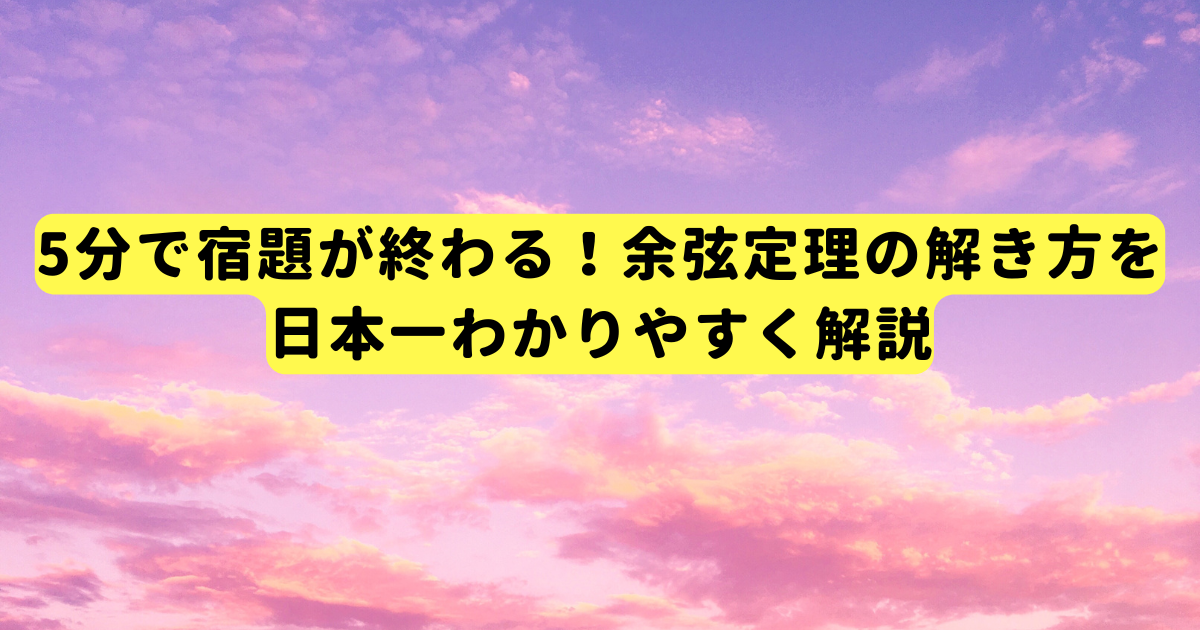
お、また数学で悩んでるな。大丈夫、余弦定理なんてマジで怖くないぞ。
「数学の宿題、余弦定理の問題で手が止まってないか?」
教科書のややこしい説明は一回忘れて、俺の言う通りにやってみな。大丈夫、余弦定理は**「2パターンの公式に、数字を当てはめるだけ」**で絶対に解ける。
このページは、難しい証明や理論は全部すっ飛ばして、君が**「最速で答えにたどり着く方法」**だけを書いた、カンニングペーパーより役立つ究極のガイドだ。
この記事を読めば、君は…
- 余弦定理を使うべき問題が一瞬で見抜けるようになる。
- 辺の長さを求める問題がスラスラ解けるようになる。
- 角の大きさを求める問題もマスターできる。
さっそく、5分で宿題を終わらせにいこうぜ!
まずはこれだけ!余弦定理は「この2パターン」でしか使わない
余弦定理をいつ使うのか、ここでハッキリさせておこう。使う場面は、驚くほど少ない。たったの2パターンだ。
- 2つの辺とその『間の角』がわかっている時
- 3つの辺の長さがすべてわかっている時
このどっちかだったら、迷わず余弦定理の出番だ。逆に、これ以外のパターンの問題だったら、だいたい「正弦定理」を使うことになる。シンプルだろ?
🎨 デザイナー向け指示書:インフォグラフィック
件名: 余弦定理を使う「2つの場面」
目的: 読者が問題文を見た瞬間に、余弦定理を使うべきかどうかを判断できるようにする。
構成要素:
1. タイトル: 余弦定理の出番はこの2つだけ!
2. 左の図: 三角形の2辺(a, b)と、その2辺に挟まれた角(C)をハイライトしたイラスト。キャプションは「パターン① 2辺と『間の角』がわかる時」
3. 右の図: 三角形の3辺(a, b, c)すべてをハイライトしたイラスト。キャプションは「パターン② 3辺すべてがわかる時」
4. 補足: 中央に「この形を見たら、ヨゲン・テイリ!」という吹き出しを追加。
デザインの方向性: 親しみやすい手書き風のイラスト。重要な辺と角は赤色で強調するなど、視覚的に分かりやすく。
参考altテキスト: 余弦定理を使う2つのパターンを示した図解。左は2辺と間の角が分かっている三角形、右は3辺すべてが分かっている三角形。
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: 「正弦定理と余弦定理、どっちを使うか?」で迷ったら、「3つの辺が関係するかどうか」で判断しよう。
なぜなら、俺がこれまで見てきた中で、生徒が一番多く質問するのが、この「どっちを使えばいいの?」問題だからだ。正弦定理は「向かい合う辺と角のペア」が主役だけど、余弦定理は「3つの辺」が必ず式に入ってくる。だから、問題に3つの辺が登場したら、まず余弦定理を疑うのが正解への近道だぜ。
【パターン①】辺の長さを求める問題の解き方(3ステップ)
じゃあ、早速メインディッシュだ。君の宿題も、たぶんこのパターンじゃないか?
例えば「△ABCにおいて、a=8, b=5, C=60°のとき、辺cの長さを求めよ。」みたいな問題。
これを一緒に解いてみよう。ステップはたったの3つだ。
使う公式はこれだ!
c² = a² + b² - 2ab cosC
ステップ1:公式に、わかっている数字をそのまま入れる
この公式のaに8を、bに5を、Cに60°を入れるだけ。見たまま入れるのがコツだ。
c² = 8² + 5² - 2 × 8 × 5 × cos60°
ほら、ただの計算式になっただろ?
ステップ2:計算できるところを、落ち着いて計算する
8² は 64、5² は 25 だな。
cos60° は 1/2 になる。これはよく出てくるから、覚えちゃおう。
c² = 64 + 25 - 2 × 8 × 5 × (1/2)
c² = 89 - 80 × (1/2)
c² = 89 - 40
c² = 49
ステップ3:最後に「²」を外す
c²が49だから、cは7だな。これで終わり!簡単だろ?
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: 9割がハマるワナは、cosの値がマイナスになる時の符号ミスだ。
なぜなら、例えば角Cが120°だった場合、
cos120°は-1/2になる。そうすると、公式の最後の部分-2ab × (-1/2)は、マイナスとマイナスでプラスに変わるんだ。この符号の逆転を見落として、計算ミスをする子が本当に多い。角度が90°より大きい鈍角の時は、このワナを思い出してくれ。
【パターン②】角の大きさを求める問題の解き方(こっちも3ステップ)
次はもう一つのパターン、「3つの辺がわかっていて、角を求める」問題だ。
例えば「a=7, b=8, c=5のとき、角Aを求めよ。」みたいなやつだな。これもビビる必要はない。
使う公式はこれ!
cosA = (b² + c² - a²) / 2bc
さっきの公式を、cosAについて解きやすいように変形しただけなんだ。
表タイトル: 2つの公式は、実は同じもの!
| 目的 | 公式 | ポイント |
|---|---|---|
| 辺を求める時 | a² = b² + c² - 2bc cosA |
求めたい辺 a と、その向かいの角 A が両端にくる |
| 角を求める時 | cosA = (b² + c² - a²) / 2bc |
求めたい角 A と、その向かいの辺 a が式の最後にくる |
これも3ステップで終わらせよう。
ステップ1:公式に、数字をドン!と入れる
cosA = (8² + 5² - 7²) / (2 × 8 × 5)
ステップ2:分数の「上」と「下」をそれぞれ計算する
まず、分数の上(分子)から。
64 + 25 - 49 = 89 - 49 = 40
次に、分数の下(分母)。
2 × 8 × 5 = 80
つまり、cosA = 40 / 80 になる。
ステップ3:約分して、角度を答える
40 / 80 を約分すると 1/2 だな。
cosが1/2になる角度は… そう、60°だ。これが答え!
まだ不安な君へ!よくある質問(FAQ)
Q1. 三平方の定理(ピタゴラスの定理)と何が違うの?
A1. いい質問だな!実は、余弦定理は「三平方の定理のスーパーバージョン」なんだ。
もし角が90°(直角)だったら、cos90°は0になるだろ?そうすると、余弦定理のc² = a² + b² - 2ab cos90°の後ろの部分が全部消えて、c² = a² + b²っていう、見慣れた三平方の定理になる。つまり、直角三角形以外でも使えるようにパワーアップしたのが余弦定理なんだぜ。
Q2. 公式がごちゃごちゃして覚えられません…
A2. 全部を丸暗記する必要はないぞ。a² = b² + c² ... の形を一つだけ覚えておけばOKだ。
ポイントは、「求めたいものの『向かい側』がセットになる」ってこと。辺aの公式なら、最後にcosAがくる。辺bの公式なら、最後にcosBがくる。これさえ押さえておけば、文字が変わっても絶対に対応できる。
まとめ:もう余弦定理は君の武器だ!
どうだ、健太?もう余- 弦定理は余裕だろ!
最後に、大事なポイントをもう一回だけ確認しておこう。
- 余弦定理は「2辺と間の角」「3辺」の2パターンで使う。
- 公式は、数字を当てはめるだけの計算ゲーム。
- 計算ミス(特に符号!)にだけ気をつければ、絶対に解ける!
やればできるじゃん。君はもう、余弦定理で手が止まることはない。
この調子で、他の問題もサクッと片付けちゃおうぜ!
宿題が終わったら、次はテスト対策だ。
次につまずく可能性が高い「正弦定理」で苦戦してないか?こっちも5分で終わる攻略法があるから、見ておけよな!
→【5分でわかる】正弦定理の解き方