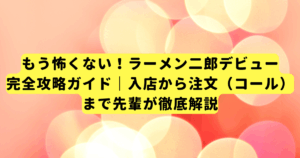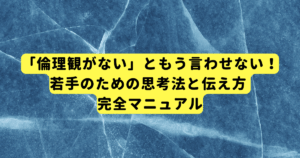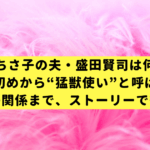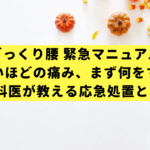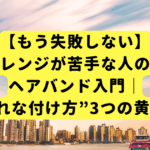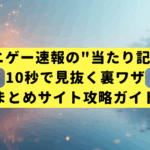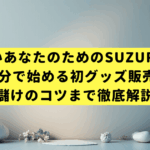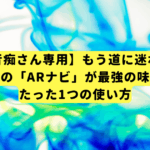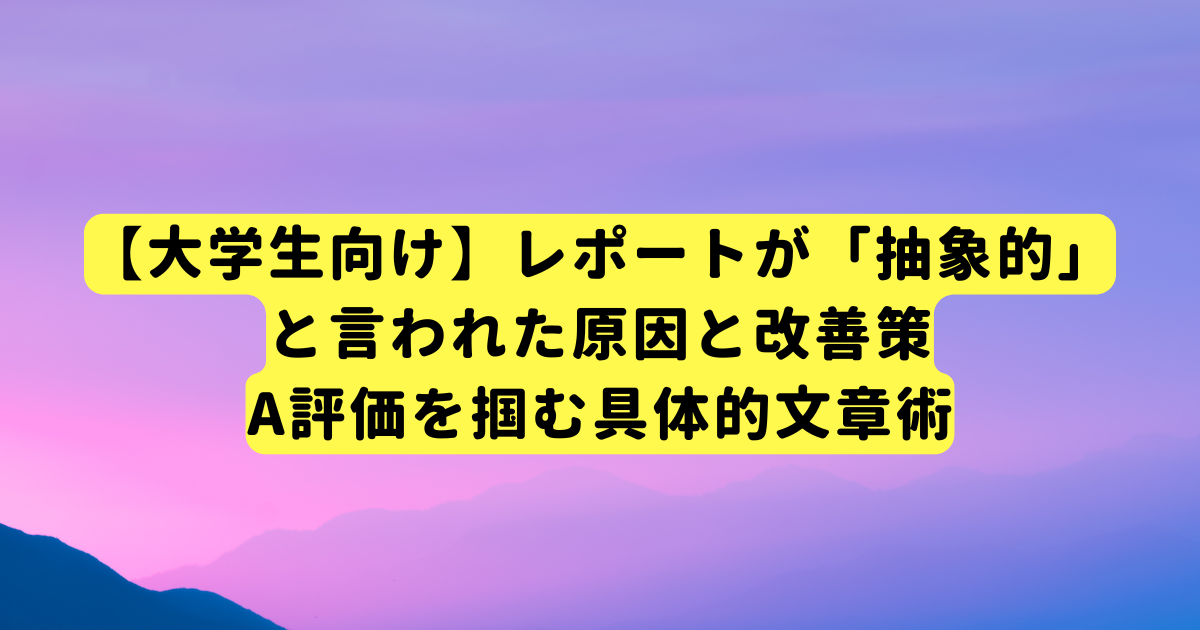
教授からの「もっと具体的に」というフィードバック。どう直せばいいか分からず、PCの前で手が止まっていませんか?
レポート作成、お疲れ様です。アカデミック・ライティング・コーチの佐藤です。かつて大学で多くの学生を指導してきましたが、その悩みは本当に良く分かります。ご安心ください。それはあなたの能力が低いからではなく、大学で求められる「書き方の型」をまだ知らないだけなのです。
この記事の結論を先にお伝えすると、あなたのレポートに足りないのは、難しい知識ではなく、主張を支える**「客観的な事実」と「根拠の示し方」という技術**です。
この記事は単なる言葉の解説ではありません。あなたのレポートをA評価に引き上げるための、具体的なBefore/After例文が満載の実践的ガイドです。この記事を読み終える頃には、あなたは以下の状態になっています。
- 自分の文章の「抽象的な箇所」を特定できるようになる。
- 明日から使える、具体的な文章改善テクニックが身につく。
- 教授を納得させる、論理的なレポート構成の型がわかる。
一緒に、その「書き方の型」をマスターしていきましょう。
なぜ? あなたのレポートが「抽象的」と評価されてしまう3つの根本原因
まず、問題の根本原因を探ることから始めましょう。教授があなたのレポートを「抽象的だ」と指摘する背景には、主に3つの原因が隠れています。自分の文章がどれに当てはまるか、チェックしてみてください。
原因1: 「感想」と「事実」が混ざっている
これは最も多くの学生が陥るパターンです。「〜は重要だ」「〜は大きな影響を与えた」といった表現は、書き手の「感想」であり、客観的な「事実」ではありません。学術的な文章では、感想ではなく、誰が見ても同じように解釈できる事実に基づいて主張を組み立てる必要があります。
- 悪い例: 「スマートフォンの普及は、私たちのコミュニケーションに大きな影響を与えた。」
- (→「大きい」かどうかは個人の感想であり、客観的な事実ではない)
原因2: 主語が曖昧で大きい
「人々は〜」「現代社会では〜」といった大きな主語を使うと、文章の焦点がぼやけてしまいます。レポートでは、「誰が」「何が」をできるだけ限定し、明確に記述することが求められます。
- 悪い例: 「人々は、異文化を理解することが大切だと考えている。」
- (→「人々」とは具体的に誰のことか? 全員がそう考えているのか?)
原因3: 主張を裏付ける「根拠(出典)」がない
たとえ正しい情報を書いていても、その情報がどこから来たものなのかを示さなければ、それはあなたの「意見」と見なされてしまいます。レポートの信頼性は、主張の一つひとつに信頼できる根拠(文献やデータ)が紐付いているかどうかで決まります。
- 悪い例: 「日本では、非言語的なコミュニケーションが重視されると言われている。」
- (→誰が言っているのか? その説の典拠は何か?)
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: まずは自分の文章の「事実」と「意見」を、マーカーで色分けしてみてください。
なぜなら、この点は多くの人が無意識にごちゃ混ぜにしてしまっているからです。「『事実と意見を分けるのが難しい』という相談は非常に多いですが、客観的なデータや文献から引用した部分(事実)と、それを受けて自分が考えたこと(意見)を視覚的に分離するだけで、思考は驚くほど整理されます。この知見が、あなたの成功の助けになれば幸いです。
A評価レポートの公式:「抽象」を「具体」に変える3つの鉄則
原因が分かれば、対策は明確です。ここからは、誰でも実践できる、抽象的な文章を具体的に書き換えるための3つの鉄則をご紹介します。この「型」を身につけるだけで、あなたのレポートは劇的に変わります。
鉄則1: 形容詞を「数字・固有名詞」に置き換える
「とても」「大きな」「様々な」といった形容詞や副詞は、感想に見えやすいため極力避けましょう。代わりに、具体的な「数字」や「固有名詞」に置き換えることで、文章は一気に客観性を増します。
- Before: 「その企業の業績は、非常に伸びた。」
- After: 「その企業の売上高は、2020年から3年間で50%増加した。」
鉄則2: 主張には必ず「出典」を添える
自分の主張ではない事実やデータ、専門家の見解を記述する際は、必ず「誰が」「どこで」言っているのかという出典を明記する癖をつけましょう。これにより、文章の信頼性が飛躍的に高まります。
- Before: 「対話が重要だと言われている。」
- After: 「異文化経営学者のA氏は、その著書**『〇〇』の中で「対話こそが相互理解の第一歩である」と述べている(A, 2018)**。」
鉄則3: 5W1Hで「自己添削」する
自分の書いた文章が具体的かどうかをチェックする最も簡単な方法は、5W1H(Who, When, Where, What, Why, How)を使って自問自答することです。これらの問いに答えられない箇所が、具体化すべきポイントです。
- 問いかける前の文章: 「グローバル化は、文化に影響を与えた。」
- 自己添削後: 「1990年代以降(When)、**インターネットの普及(How)に伴うグローバル化で、特に若者層(Who)**を中心に、**食文化(What)**の面で影響を受けた。」
これらの鉄則を実践することで、あなたの文章は「感想文」から「論証文」へと進化します。
**
🎨 デザイナー向け指示書:インフォグラフィック
件名: 「抽象」から「具体」への文章変換プロセス
目的: 読者が抽象的な文章を具体的な文章に書き換える際の思考プロセスを、3ステップで視覚的に理解できるようにする。
構成要素:
1. タイトル: A評価レポートの文章作成フロー
2. ステップ1: 感想を捉える: アイコン(吹き出し)と共に「影響が大きかった」という元の文章を配置。
3. ステップ2: 事実化: アイコン(虫眼鏡)と共に「なぜ大きい?→数字で示そう」という思考プロセスを記述。「売上が50%増加」という具体的な文章に変換。
4. ステップ3: 根拠付け: アイコン(本)と共に「そのデータはどこから?→出典を示そう」という思考プロセスを記述。「(出所: 〇〇社 決算報告書)」という根拠を追加。
5. 補足: 最終的に完成した具体的な文章を一番下に配置する。
デザインの方向性: シンプルで分かりやすいフラットデザイン。大学のレポートというテーマに合わせ、落ち着いた青や緑を基調とする。
参考altテキスト: 抽象的な文章を具体的にする3ステップのフロー図。感想を事実に変え、根拠を加えるプロセスを示している。
実践!レポートを劇的に改善するBefore/After例文クリニック
理論を学んだら、次は実践です。ここでは、大学の主要な学問分野で学生が書きがちな「抽象的な悪い例(Before)」と、「3つの鉄則」を適用して改善した「具体的な良い例(After)」を比較してみましょう。
分野別・レポート文章改善 Before/After
分野 抽象的な悪い例 (Before) 具体的な良い例 (After) 改善ポイント 文学 シェイクスピアは、多くの作品で人間の複雑な感情を描いた。 シェイクスピアは、四大悲劇の一つ**『ハムレット』において、主人公ハムレットの「生きるべきか、死ぬべきか」という独白**を通じ、復讐心と道徳の間で揺れ動く内面の葛藤を描写した。 「多くの作品」→『ハムレット』、「複雑な感情」→具体的なセリフや状況 経済学 近年、キャッシュレス決済が急速に普及している。 経済産業省の調査によれば、日本のキャッシュレス決済比率は**2012年の15.1%から2022年には36.0%**へと、10年間で2倍以上に上昇した。 「近年」「急速に」→具体的な統計データと期間、「普及している」→出典の明記 心理学 幼少期の経験は、その後の人格形成に大きな影響を与えると言われている。 発達心理学者のエリク・H・エリクソンは、幼児期(1-3歳)における自律性の獲得が、その後の自己肯定感の基礎となると指摘している(エリクソン, 1963)。 「〜と言われている」→提唱者(エリクソン)の明記、「幼少期」→具体的な発達段階(幼児期)
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: 文献を引用した後は、必ず「この事実から私はこう考える」という、あなた自身の考察を一文加えてください。
なぜなら、多くの学生がやってしまいがちな失敗は、複数の文献の内容をただ繋ぎ合わせただけの文章にしてしまうことだからです。それでは単なる「情報のまとめ」であり、あなたの「レポート」ではありません。引用はあくまで自分の主張を補強するための道具です。この知見が、あなたの成功の助けになれば幸いです。
レポート提出前の最終チェックリスト
□ 形容詞や副詞(大きい、とても、など)を、具体的な数字や固有名詞に置き換えたか?
□ 主語が「人々」や「社会」など、大きすぎないか?
□ 自分の意見ではない事実やデータには、すべて出典を明記したか?
□ 各段落は「主張→根拠→考察」の流れになっているか?
□ 全ての文章は、5W1Hの問いに答えられるか?
それでも迷うあなたへ。「抽象的」に関するQ&A
最後に、学生の皆さんからよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 抽象的な思考のメリットはないのですか?
A. もちろんあります。物事の本質を捉え、複雑な情報を単純化する「抽象化思考」は、学問を探求する上で非常に重要です。しかし、レポートでその思考の成果を示す際には、再び「具体化」して説明する必要がある、ということです。
Q. ビジネスシーンでも同じ注意が必要ですか?
A. はい、全く同じです。上司への報告やプレゼンテーションで「売上がかなり好調です」と伝えるより、「売上が前月比で120%達成しました。特にA商品の貢献が大きいです」と伝える方が、遥かに説得力があります。具体的に話すスキルは、社会に出てからも必須の能力です。
Q. どこまで具体的に書けばいいのか、終わりが見えません。
A. 良い質問ですね。目安は「その分野を初めて学ぶ人が読んでも、追加の質問をせずに理解できるレベル」です。レポートのテーマや文字数によっても変わりますが、常に「読者」を意識することが、適切な具体性の判断基準になります。
まとめ:あなたのレポートは、もっと良くなる
この記事でお伝えしてきたことを、最後にもう一度確認しましょう。
- レポートで評価されるのは「感想」ではなく**「事実」と「根拠」**です。
- 抽象的な言葉を避け、「数字・固有名詞」に置き換え、「出典」を添えることを徹底してください。
- この「具体的に書く型」は、大学だけでなく社会に出てからも一生使える強力なスキルになります。
教授からのフィードバックは、あなたを否定するものではなく、あなたの思考をより深く、鋭くするための「成長への招待状」です。今日学んだ技術を使えば、あなたのレポートは必ず良くなります。自信を持って、その一歩を踏み出してみてください。
まずは、あなたのレポートの1段落だけでも構いません。今回紹介したテクニックで、文章を書き換えてみましょう。その小さな成功体験が、レポート全体を完成させる大きな力になるはずです。